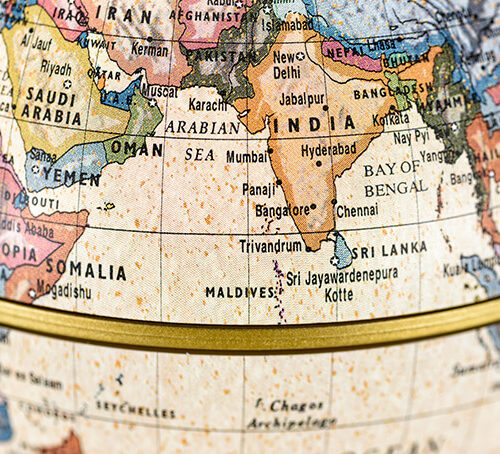- 商標
- インド
2025.10.21
商標部 妹尾 真理
2025年8月下旬から9月初旬にかけて、NGB商標部員3名(妹尾、横田、笠井)はインドおよびバングラデシュの特許庁、ならびに主要代理人事務所(インド7事務所/バングラデシュ5事務所)を訪問しました。両国とも近年、経済成長とともに知的財産制度の整備が急速に進んでおり、現場では新しい技術導入や制度改革の動きが活発化しています。本稿では、現地で得られた最新の動向と印象をお伝えします。
■ インド:AI活用と制度改革が進む商標審査体制
インド特許意匠商標総局(CGPDTM)では、近年、審査の効率化と透明性向上を目的に、AI技術の導入 や 審査官増員 が進められています。現時点で商標審査官は約190名ですが、今後3〜5年でさらに260名増員する計画とのことです。AIを活用した商標類似検索は、わずか数秒で数百万件のデータを横断的に検索できる仕組みが試験的に導入されており、将来的には審査プロセスの大幅な短縮が見込まれます。また、更新リマインド通知の自動化や調停制度(Mediation)の導入など、「利用者に寄り添う制度改革」 も進行中です。現地代理人からは、こうした改革を前向きに評価する声が多く聞かれました。一方で、「AIによる検索結果を過信せず、最終判断には人の専門知識が不可欠」との見解もあり、テクノロジーと実務経験の融合が課題として挙げられました。また、出願から登録までの期間は通常12〜14か月ですが、早期審査請求制度を利用すれば3〜4週間で審査が開始されることもあるとのことで、手続の柔軟性が高まっている印象を受けました。さらに、模倣品・侵害対応を強化するため、AIを使わない独自の監視サービスや、ドメイン凍結を迅速に行う「動的差止命令(Dynamic Injunction)」なども整備されています。商標実務の現場では、データベースの一元化、自動化ツールの導入など、各事務所が独自の工夫を凝らしており、知財業務の効率化と品質向上の両立を模索している様子がうかがえました。また、インドにおいて、古い異議申立案件の長期滞留に関する問題が長年の課題となっていますが、特許庁長官、現地代理人の双方が強い問題意識を持っており、滞貨の解消に向けた方策を実行する動きも確認できました。現地では知財人材の育成にも力が入れられており、若手弁護士やエンジニアが積極的に新技術を学ぶ姿勢が印象的でした。

■ 現地の生活と文化:多様性に満ちたインドの日常
デリーでは宗教・文化・食習慣が共存する多様な社会が広がっています。ベジタリアン人口は全体の4〜6割に上り、牛肉を食べることはほとんどありませんが、乳製品は広く受け入れられています。主食はナンよりもチャパティが一般的で、屋台では豆や野菜のスパイス煮込みが人気を集めていました。また、健康志向の高まりから「マクナ(蓮の実)」などのスーパーフードが注目され、日本食レストランも増加傾向にあります。巻き寿司や照り焼き風料理が好まれており、日本文化への関心の高さを感じる場面も多くありました。
■ バングラデシュ:オンライン化の萌芽と現場の努力
バングラデシュ特許意匠商標局(DPDT)では、2025年6月にWIPOの支援を受けて新システムIPAS4を導入。オンライン出願が開始され、今後は更新手続の電子化も予定されています。これまで完全に紙ベースで運用されていた庁業務がようやくデジタル化の一歩を踏み出した形です。しかし現実には、審査官はわずか12名、未処理案件は22,000件超と、人手不足が深刻 です。原簿から未更新商標が削除されていないため、失効したはずの商標が引用される事例もあり、制度面・運用面での改善が求められています。一方、代理人側ではこうした課題に対応するため、庁にスタッフを常駐させて紙ファイルの探索や審査促進を支援するなど、現場レベルでの努力が際立っていました。報告書作成を自動化するシステムを自社開発するなど、IT活用の工夫も見られます。庁の建物は老朽化しているものの、職員や代理人の方々は誠実で前向きな姿勢を持ち、知財制度をより良くしようという強い意欲を感じました。現地の食文化にも触れる機会があり、国魚ヒルシャ(Hilsa)の豊かな味わいと、もてなしの温かさが印象に残りました。
首都ダッカの街並みは混沌としていますが、その中にも新しい技術や仕組みを取り入れようとする勢いが感じられます。代理人事務所の幾つかは家族経営で、靴を脱いで勤務するなど、独自の文化が根付いていました。日本企業に対する好意的な姿勢も強く、バングラデシュでは「日本は独立後に最初に支援してくれた国」との声もあり、両国とも日本との連携を重視していることが印象的でした。インドは「制度の整備とスピード」が特徴的であり、技術的・組織的な成熟が見られます。一方、バングラデシュは「誠実さと成長意欲」にあふれ、発展途上ながらも確実に進化している段階です。両国に共通するのは、知的財産への関心が高まり、国としての競争力強化に知財を位置づけようとする姿勢です。今回の訪問を通じて、制度の成熟度に差はあれど、アジア各国がそれぞれの立場で知財保護を重視し、社会や経済の発展に結びつけようとしていることを肌で感じました。特に、現地の人々の真摯で温かい対応や、前向きに変化を受け入れる姿勢は、今後の国際的な知財協力の礎となるものであると感じました。